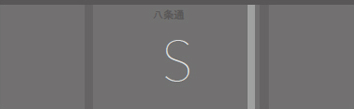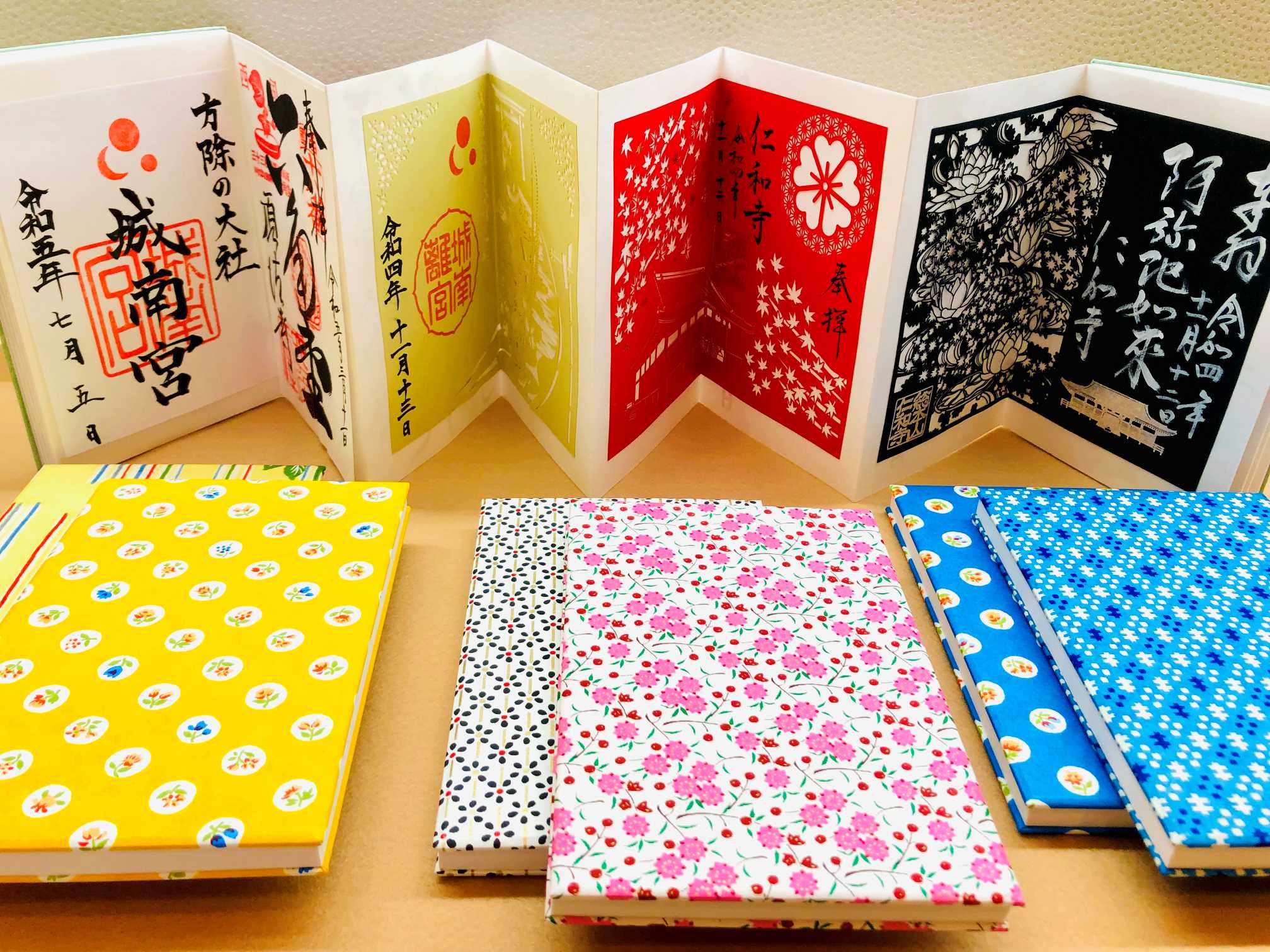地図から探す
 検索中
検索中
27 件のページが見つかりました。

| 休業日 | 日曜日 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 工房情報 | 蘇嶐窯は、京都・清水焼と福岡・小石原焼に伝わる技術をそれぞれ受け継ぐ職人が互いの技を融合し、夫婦で作陶活動をしています。 蘇嶐窯の青磁は「練り込み青磁」といい、生地に顔料を練り込み釉薬を掛けることで、深みのある青を表現しています。そこに小石原焼の技法の「飛かんな」を入れることで、削られた土の溝に釉薬が溜まり規則的な文様が浮かび上がります。こうして他にはない新しい青磁の世界を模索しています。蘇嶐窯が目指す色は、雨上がりの空のような青さです。この澄んだ青をたくさんの人に伝えたいという想いから、美しさと機能性を兼ね備えた商品作りに取り組んでいます。近年では海外販路開拓にも力を入れ、海外で得た経験を新たに作品に落とし込み、洋食器の製作も行っています。また蘇嶐窯オリジナルのストーリーのあるアクセサリーなど幅広いラインナップでの商品展開を行っています。 |

| 休業日 | 日・土曜日・祝日 |
|---|---|
| 営業時間 | 08:00~17:00 |
| 工房情報 | 髙木漆工は塗師髙木望が京都で13年の修業を経て2017年に立ち上げた京漆器の技法を受け継ぐ新しい工房。 京漆器は、794年の平安遷都により奈良から漆文化が伝わり花開いた。茶の湯と共に発展してきた経緯から、わび・さびといった内面的な美しさを持ち、抹茶を入れる棗、菓子器、盆などさまざまな形で茶道に関わり、目の肥えた茶人たちがそれを求めた。 工房では茶道具に加え料亭などで使用する食器類、美術工芸品の修理修復などを手がけ、また祇園祭の大船鉾の復元の漆塗りに携わるなど幅広いニーズに応えている。 |
辻が花染め工房 絵絞庵
-京鹿の子絞-
見学制作体験買い物
詳細表示

| 休業日 | 日曜・祝日 (祝日は事前連絡にて応相談) |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 工房情報 | 「幻の染め」を今に伝える
安土桃山時代に隆盛し、絢爛豪華な着物の代名詞となった「辻が花」は現存資料が少なく「幻の染め」とも呼ばれている。絵絞庵は辻が花を現代に甦らせた先代の故福村廣利に師事した福村健が制作をおこなう染工房。 生地を縫い、括り、絞って絵模様などを染め分ける「絞り染め」を基調に描き絵などを施すことで鮮やかな色彩と絵画的な模様を表現していく。 美しい水に恵まれた洛北の地で、伝統の手仕事を守り続けている。
福村健:・日本工芸会準会員
・京都市未来の名匠
・京都染色美術協会会員
|
株式会社 堤淺吉漆店
-京漆器-
見学制作体験
詳細表示

| 営業時間 | 08:50~17:30 第2・第4土曜日 休業。 12月、1月は土曜休みが変わります。 |
|---|---|
| 工房情報 | 漆は漆の木の樹液。10年~15年の成木から牛乳瓶1本分ほどしか採取出来ない貴重な自然の恵みです。 その採取して頂いた漆を仕入れ、精製・調合しています。時代とともに精製技術や設備は進歩し、創業当初の手クロメからクロメ鉢による機械式の 精製に変化しました。創業当初からの変わらぬ想い「漆を一滴も無駄にしてはならない」という漆への感謝。お客様のニーズにお応えする漆を提供 しています。
|

| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 工房情報 | 京焼・清水焼窯元・陶葊は大正11年、京都の東山泉涌寺(ひがしやませんにゅうじ)で創業しました。現在、本店の工房で製造にたずさわる職人は、成形や絵付けで約20人ほど。作業はすべて手仕事となっており、京都の窯元としては屈指の大所帯となっています。 陶葊の手がける清水焼は、鮮やかな発色とほかにはない強度が特徴です。清水焼は本焼きをした上に絵をつける「上絵付け」で知られていますが、陶葊では釉薬を塗る前に彩色する「下絵付け」を採用。さらに1,200度という高温で焼くことで、強度のある清水焼を作ることに成功しました。高温で焼くと鮮やかな色味を出すのが難しいのですが、下絵に使う絵の具から開発することで、雅びな色味はそのままに傷つきにくさも実現。現在の陶葊の基礎となる技術を確立しました。現在は、四代目である土渕善亜貴が陶葊の当主となっており、多種多様な結晶の形が楽しめる「花結晶」を開発・確立いたしました。(同社ホームページより) 京焼・清水焼窯元陶あん本店で展開される、工房での陶芸教室での体験の中で、「京都工房コンシェルジュ」では初心者向けのプログラムを中心にご紹介します。 |

| 休業日 | 日・祝日(1~9月第2・第4土曜) 年末年始(12月25日~1月9日 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 工房情報 | ほのかに揺れる炎は手仕事の証 各宗派総本山が集まる京都において、欠かすことができない手仕事が和蝋燭。原材料は櫨の実から採取した木蝋。純植物性のため、油煙が少なく、煤が出にくいのが特徴だ。明治20年(1887)より和蝋燭の製作を手掛ける中村ローソクでは、木型で成型した蝋燭生地に、熱した蝋を素手で擦り付けていく「清浄生掛け製法」を守り、1本ずつ手仕事で和蝋燭を仕上げていく。伝統製法でつくられた和蝋燭は内部が空洞のため炎がほのかに揺らぐ美しさを持つ。 |